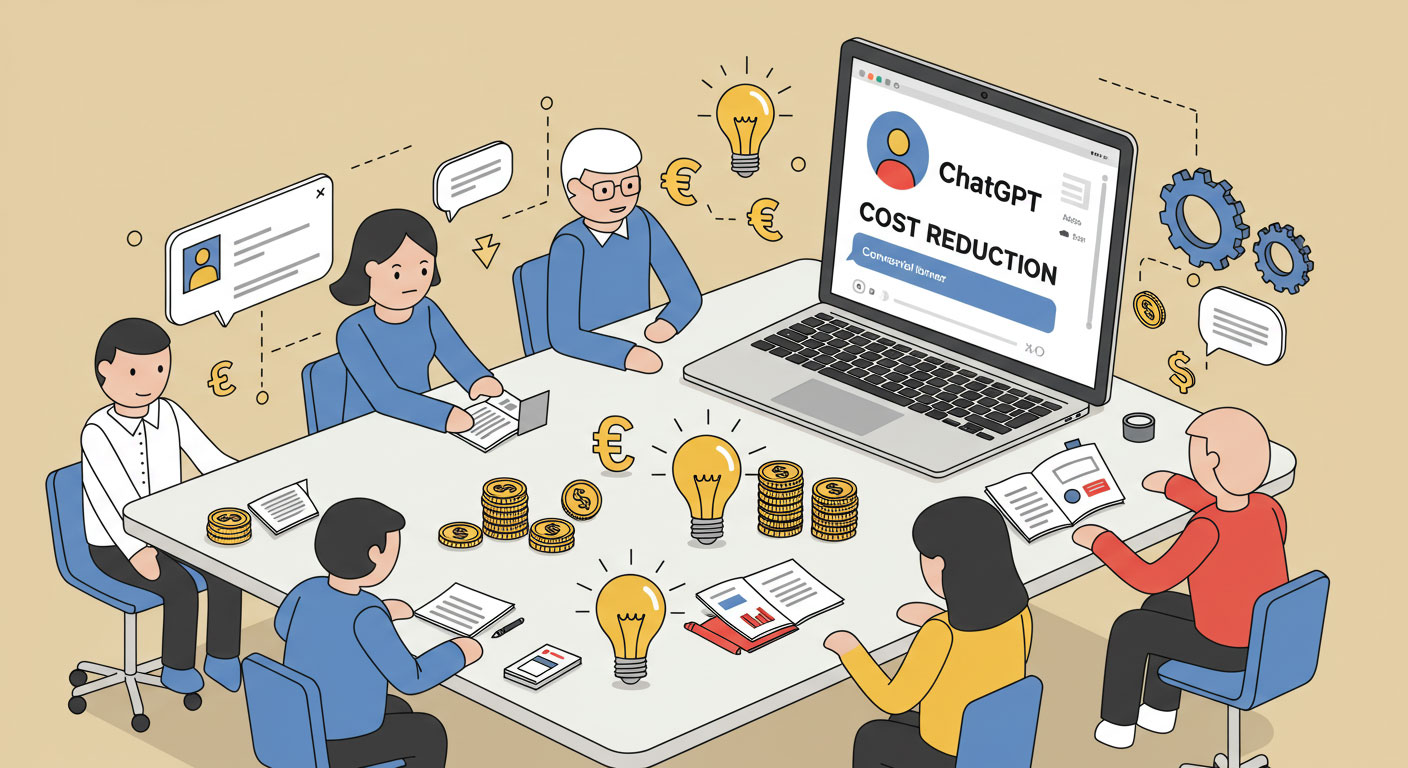ChatGPTで“経費削減”アイデアを提案させる方法 何を削るか」よりも、「どう削らせるか」の時代へ
はじめに:コストカットに“知恵”を使う時代がきた
「経費削減」。
この言葉を聞くと、多くの人は「無駄なものを削る」「予算を絞る」「人件費を抑える」といったイメージを持つでしょう。
けれど、いまや時代は変わりました。
単純な“節約”では、限界がある。
むしろ「何をどう削るか」を考える時間や手間の方が、コストになる。
ここで登場するのが、ChatGPTのような生成AIです。
ただし、ただ「経費削減のアイデアを出して」と命令しても、表面的な回答しか返ってきません。
ポイントは、“質問の仕方”にあります。
この記事では、ChatGPTを使って、誰も思いつかないような経費削減のアイデアを引き出す“思考設計術”を、第三者視点で徹底的に掘り下げていきます。
経費削減は、もはや“遊び”である
本気で言っています。
経費削減は、もはや「遊び」として取り組んだ方が成果が出るのです。
理由はシンプル。
削減できるコストの多くは、“常識”の中に埋もれているから。
ChatGPTにアイデアを出させる際、最も大切なのは、「前提を壊す質問を投げること」。
真面目な問いには、真面目な答えしか返ってきません。
例えば、以下の2つのプロンプト(質問)を比べてみましょう。
- ①「中小企業が今すぐできる経費削減策を教えてください」
- ②「会社の経費を“ふざけて減らす”方法を10個、超真面目に考えてください」
②の方が圧倒的にユニークな答えが返ってきます。
AIは、問いの「温度感」や「遊び心」にも応えてくれるのです。
ChatGPTに“型破り”なアイデアを出させるテクニック集
テクニック①:「役職になりきらせる」
例:
「あなたは架空の“経費削減専門のCFO(最高財務責任者)”です。固定費を1/3に減らすという命令を受けています。何をしますか?」
役職や立場を与えると、ChatGPTはそのロールプレイに従ってアイデアを出します。
この“役割設定”を工夫することで、視点のバリエーションが生まれます。
テクニック②:「過激な制限条件を与える」
例:
「オフィスの電気代をゼロにする方法を“犯罪にならない範囲”で考えて」
常識では不可能と思える条件をあえて与えると、AIは“妥協”のアイデアではなく、“工夫”のアイデアを出してきます。
テクニック③:「時代・国・文化を変える」
例:
「江戸時代の商家に生まれ変わったと仮定して、経費を減らす工夫を10個挙げて」
「文化」「宗教」「季節」など、条件をずらして質問すると、AIの“抽象的思考”が引き出されます。
テクニック④:「逆に増やす発想をさせる」
例:
「コストを“あえて倍にする”ことで、最終的に得する方法を教えて」
これは一見、逆効果に見えますが、「広告費を倍にして、営業人員をゼロにする」など、“逆転の発想”が出てくることがあります。
テクニック⑤:「子どもに説明させる」
例:
「あなたは小学5年生です。学校で『会社の経費を減らす作文』を書くことになりました。どう書きますか?」
AIは単純化・擬人化・ユーモアを織り交ぜて、思いもよらない視点からの答えを出してきます。
実際に引き出せた「突拍子もない」アイデア事例
- 会議を「歩きながら」にする
→ 電気代、椅子の劣化、時間のロスを減らせるという発想。 - 社内通貨「ワクポイント」を導入
→ 社内行動をゲーム化し、節約行動を自然と促進。 - 「月に一度、全員逆役職の日」
→ 経営層が現場を体験することで、リアルな削減策が生まれる。
ChatGPTの出力を「発想のたたき台」として活用する
ここで重要なのは、ChatGPTの出す答えを「そのまま実行する」のではなく、「発想のたたき台」として使うこと。
AIはあくまで“補助脳”。「正解」を与える存在ではなく、「問いを深める」ための存在です。
忘れてはならない“コスト削減の副作用”
- モチベーションの低下
- 品質の劣化
- 顧客満足度の低下
- 社内の空気がギスギス
こうしたリスクを避けるには、以下のような質問をAIに投げかけましょう。
「社員のモチベーションを下げずに経費を10%削減する方法を、心理学と組織論の視点から考えて」
経費削減に“AIとユーモア”を取り入れる意味
ChatGPTのやり取りそのものが、経費削減の空気をポジティブにします。
たとえば、「経費削減会議」を「AIと遊ぶ雑談会」として開催してみると、心理的ハードルが下がり、本質的なアイデアが出やすくなるかもしれません。
おわりに:AIは「コストを削る道具」ではなく、「価値を生む相棒」
経費削減の本質は、コストをゼロにすることではありません。
限られたリソースで価値を最大化する「戦略思考」そのものです。
ChatGPTは判断を下す存在ではなく、
あなたが考えるための「新しい地図」を描いてくれる存在です。
もし、経費削減に限界を感じているのなら、
「何を削るか」よりも「どう削らせるか」の視点で、
AIに問いをぶつけてみてください。
きっと、驚くような答えが返ってくるはずです。
それこそが、「AI時代の経営戦略」の第一歩なのです。